i-compass家づくりの羅針盤という
統計学・心理学・ラダリング法で
顧客分析できる
システムを使って、
地域工務店の営業を支援している
コンサルタントの福浦です。
デザインを考える上で
シンプルイズベストと言いますが
なぜ、いいのか?
この疑問をしてみると
多くの回答は
雑音がない
ノイズがない
すっきりしている
スマートなデザイン
などなど形容詞を多くが
コトバとして利用しています。
ですが、それではなぜいいかを
うまく表現できていないように
思います。
シンプルイズベストがなぜいいか?
人間の視線は、変化に強制的に動かされる
のです。
なので、繁華街や自己主張の強いデザインは
変化を多く多用しています。
目立つ、奇抜、明るさ、点滅
カタチの違うもの
線が多い
区分けが多い
要素がたくさんある
色の変化
などなど、を多く使って
変化を助長しています。
その変化に視線が強制的に動かされるのです。
それは、非日常的デザインになり
視線が強制的に動かされると
高揚感が出てきます。
この高揚感が、いわゆるテンションが上がる
状態です。
テンションが上がると
心の高揚が強制的に作用して
混乱が生じます。
家のデザインとして
非日常的なデザインですと
心の乱れが思考停止状態
つまり、脳が混乱することになり
高揚感を醸し出してしまい
落ち着かない、休まらない、癒されないという
ことになります。
なので、シンプルイズベストというのは
なるべく変化をなくすことがデザインとして
必要になり
スウィッチ、コンセント
壁と天井の線や、見えない線、は
続けること
また、面(壁)などは目地を少なくする
大きな面には、目地を少なくしても
OKですが
空間が狭い時には、目地を多く入れることで
広く感じる遠近法を利用する
だから、トイレや洗面所などの
狭い空間に、モザイクタイルを
利用するのはこの効果です。
このシンプルイズベストは
子育てする家にとっては必須です。
大人の右脳は
変化が多少あっても、経験で対応できますが
子どもの脳にとっては、変化が多いことは
脳の混乱を招き、ココロの乱れを生じさせます。
心の乱れは、脳の思考停止になり
自己表現をしなくなるようになっていく。
日常のデザインで必要な絶対要素は
変化の少ないデザインにすることです。
ですが、このシンプル過ぎる家では
飽きてしまう。
逆になりますが、飽きのこないデザインには
チョット変化させる。
この変化は、全体のデザインの1割程度にする
その変化は入れ替え可能なモノ
観葉植物や、照明器具(スタンド)カーテンなどで
行う。
その割合も、全体の視界の2割程度
この割合が日常のデザインの
飽きの来ないシンプルイズベストに
なってきます。
シンプルイズベスト、日常のデザインには
マストで考えるべき内容です。
この説明をちゃんとしてデザインしてほしいです。
同じようなものに、断捨離があります。
断捨離のイメージは
まず、いらないものを捨てることだと思っている
方々も多いかと思いますが
この断捨離という言葉は
ヨガの、断行、捨行 離行から
きた言葉で
日本人の造語になります。
また、もともとは仏教用語で修業を
さした言葉からきています。
断捨離は、まずは捨てることではなく
入ってくるものから断つことから
はじめるのです。
モノが無くなるからすっきりするのではなく。
捨てることによって、ココロが納まるから
すっきりするのです。
物質的なものではなく、実は心の納まりの
問題なのです。
=================
i-compass家づくりの羅針盤住宅
セールスメソッド
驚くほど顧客が理解できる。
統計学+心理学+ラダリング法で
深層心理を理解し、
提案するものがすぐわかる。
そんな営業メソッドです。
お問い合わせはこちらから
合同会社アトラクトパートナーズ
代表 福浦 祐一
attract@fukuurayuuichi.net
090-8890-3832
ご相談は、まずはメールにてお願いします。
===================


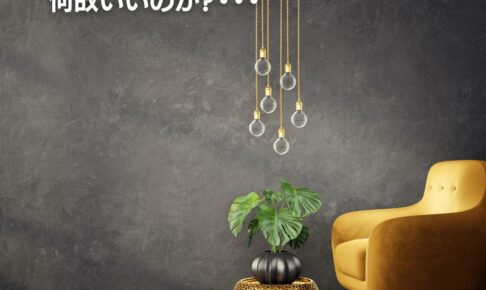











コメントを残す